![]()
 |
���E��킩��₷���I �������[������ |
|
| �`���ꂩ��}�[�W�������o�������l�ց` |
![]()
 �������[�����w�ԑO�Ɂc
�������[�����w�ԑO�Ɂc
���@��������������Ƃ̂Ȃ��l�́A�u�}�[�W�������ē�����v�Ƃ����܂��B�����āA���[�����悭������Ȃ��̂Ŏ����̓}�[�W�������o���Ȃ��A�ƍl���Ă���l�������悤�ł��B�������A���̍l����,�ԈႦ�ł��B
���́A�}�[�W�����̃��[���͂ƂĂ��ȒP�ł��B
�u�S�����c�P�W�����g�E�v�̃��[�������m���Ă���A�N�ł������ɖ�����ł��Ƃ��ł��܂��B
�}�[�W������ł���������{��ǂ�ł�����Ă悭�킩��Ȃ������l�͑����ł��傤�B�m���ɁA�}�[�W�����̖{��ǂ�ł��A�悭������Ȃ���������܂���B������ǂ��A����͐��p�ꂪ�����g���Ă��āA��������邾���ŁA���͔��ɒP���Ȃ��Ƃ�������Ă��邾���Ȃ̂ł��B
���Ƃ��A�����̂��Ƃɂ��Ă܂������m��Ȃ��l���A�ȉ��̕��͂�ǂƂ��܂��傤���B���ۂɖ����̖{�ɏ�����Ă�����e�ł��B
�u�`�[��|���̐H���d�|���͂Ȃ�ׂ��T���āA�ł��邾�������[���Ŏ�����d�グ�܂��傤�v
���āA�������������m��Ȃ��l���A���̕��͓ǂ݁A�`�[���̃|�����̂ƌ����Ă����������Ă������ς�킩��Ȃ��͓̂��R���ƌ����܂��B
�|���Ƃ�����ׂĂ݂Ă��A�����p�ꎫ�T�ł́u���Ƃ�����ăR�[�c�����낦�邱�Ɓv�Ƃ���A�R�[�c�Ƃ͉��Ȃ̂��A���ƂƂ́H�����ĉ����H�H�@�c�̂悤�ɂȂ�A��͂肳���ς蕪����܂���B���S�҂����p�ꂪ������Ȃ����璲�ׂĂ���̂ɁA���������ɐ��p��Ő�������Ă��āA���̂����Ȃ��ʓ|�������C���ɂȂ��Ă���̂��悭�킩��܂��B�������A�J��Ԃ��܂����A���p�ꂪ�����Ȃ葽���g���Ă��邩�番����Ȃ������ł����āA���ꂪ�Ȃ���A���́A�����̃��[�����̂͑債�ē���Ȃ��̂ł��B
�������킩���Ă���l��������O�̂悤�ɖ����p����g���Đ��������Ă��閃�����[���ł��A
���ꂩ��͂��߂Ė������n�߂悤�Ƃ����l�ɂƂ��ẮA�܂�����������O�ł͂Ȃ��̂ł��B
�{�Ȃǂ�ǂ�ł��킩�炸�ɁA�r���œ����o���Ă��܂����l���A���߂Ȃ��ő��v�ł��B
�܂��A�}�[�W�����̃��[����\���I�ɗ�������ɂ͏���������܂��I�I
�{�Ȃǂł́A���̏��Ԃ��l������Ă��炸�A���O������܂��̂ŁA������Ƃ������ɏq�ׂĂ��邽�߂ɁA�������Ă킩��Â炭�Ȃ��Ă���̂ł��B
�������Ԃ����ԈႦ�Ȃ���A�N�ł��ȒP�ɑf���������̃��[���𗝉��ł��܂��B
���̓_���ӂ܂��A�����ł̓}�[�W�����̃��[�����ȒP�ɁA�����A������₷���������Ă����܂��B
�ł́A�n�߂܂��傤�c���
���s�p������t
������@�@�P�C�Q�C�R�C�S�C�T�C�U�C�V�C�W�C�X�̏��B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() �@�i��������u�}���Y�v�Ƃ����B�j
�@�i��������u�}���Y�v�Ƃ����B�j
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() �@�i��������u�s���Y�v�Ƃ����B�j
�@�i��������u�s���Y�v�Ƃ����B�j
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() �@�i��������u�\�[�Y�v�Ƃ����B�j
�@�i��������u�\�[�Y�v�Ƃ����B�j
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() �@�i��������u���v�i���͂��j�v�Ƃ����j
�@�i��������u���v�i���͂��j�v�Ƃ����j
�i���ȏ�ɋ��������̂��}�[�W�����̃n�C�́��S��ށ��ł����j
���Ⴛ�̂O��
���āA�����̃��[���𗝉����āA�łĂ�悤�ɂȂ�ׂɂ́A��́A�ǂꂾ���̒m�����K�v�ɂȂ�̂��낤���E�E�E�H
���́A�ȉ��ɋ����邽�����R�̂��Ƃ�m���Ă��������ł悢�̂ł���B
�@ �u�S�����c�P�W�����g�E�v�̃��[����m���Ă��邱�ƁB
�A �����o���邱�ƁB
�B
�_���v�Z���ł��邱�ƁB
�@�A�B�Ƌ����Ă݂����A�B�̓_���v�Z�́A�Ƃ肠�����͏o���Ȃ��Ƃ��悢�ł��B�Ȃ��Ȃ�A�}�[�W�����͂S�l�ł��Q�[���ł��̂ŁA�S�l�̂����N���P�l�����_���v�Z���o����l���������ł悢�̂ł��B���̐l�ɂ���Ă��炢�܂��傤�B
�@����ɁA�A�̖����o���Ă��邱�Ƃ��d�v�ł���܂����A���͂�����A�m��Ȃ��Ƃ��悢�ł��B�i���S�҂́B�j�Ȃ����Ƃ����ƁA�����m�炸�ɓK���Ƀ}�[�W������ł��Ă��Ă��A�`���o���Ă������ł��ꉞ�ł��邩��ł��B�h���W�����̃��[�����̂܂܂ł���Ă���A���ꂪ�`�ɂȂ�܂��B
�@���������āA�}�[�W�����́A��ɋ������@�A�B�̂����A�@�́u�S�����c�P�W�����g�E�̃��[����m���Ă��邱�Ɓv�Ƃ������������Ă���A���ꂾ���őłĂ܂��B���ꂳ���o����A�}�[�W�����̃��[���̂W�O���͊��ɒB���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����Ă���͂ƂĂ��ȒP�ł��B
�@�Ƃ����킯�ŁA�ȉ��A�@�ƇA�ƇB��������Ă����܂��B
���Ⴛ�̂P��@�@�u�S�����c�P�W�����g�E�v�̃��[����m���Ă��邱�ƁB
�u�S�����c�P�W�����g�E�v���ĉ��H�Ƃ����l�ׂ̈ɁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�`�����ł́u�S�����c�P�W�����g�E�v�̃��[�����������܂��B�`
�}�[�W�����͂P�S�̃n�C���g���܂��B
���Ƃ��A�ȉ��̂悤�ɁA�n�C���o���o���ɕ���ł���Ƃ��܂��B
�@![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() �@�i���P�Q�P�R�P�Q�Q�S�S�R�S�T�T�j
�@�i���P�Q�P�R�P�Q�Q�S�S�R�S�T�T�j
���̂悤�ɁA�P�S�̃n�C������ł���Ƃ���B
���āA������A���ꂢ�ɐ������Ă݂܂��傤�B����Ɓc�c
�@![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() �@�i���P�P�P�Q�Q�Q�R�R�R�S�S�S�T�T�j
�@�i���P�P�P�Q�Q�Q�R�R�R�S�S�S�T�T�j
�ƂȂ�܂��B����́u�P�P�P�v[�Q�Q�Q]�u�R�R�R�v�u�S�S�S�v�u�T�T�v�́A�T�̕����ɕ����邱�Ƃ��o���邱�Ƃ�������Ǝv���܂��B
�i![]()
![]()
![]() �@
�@![]()
![]()
![]() �@
�@![]()
![]()
![]() �@
�@![]()
![]()
![]() �@
�@![]()
![]() �j
�j
�@���́A�u�P�P�P�v�u�Q�Q�Q�v�u�R�R�R�v�u�S�S�S�v���w�����c�x�Ƃ����܂��B
�����āA�u�T�T�v���w�A�^�}�x�Ƃ����܂��B
�v����ɁA�R�̂����܂���w�����c�x�B��̉���w�A�^�}�x�Ƃ����܂��B
�����āA�}�[�W�����ł�
�@�u�P�P�P�v�u�Q�Q�Q�v�u�R�R�R�v�u�S�S�S�v�u�T�T�v
�̂悤�Ɂw�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�����悢�̂ł��B�܂�A���̌`����肳������A����ł����܂��B�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�������A�P�����A��O������܂��B����͈ȉ��ɋ�����悤�Ȍ`�ł��B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() �i���P�P�Q�Q�R�R�S�S�T�T�U�U�V�V�j
�i���P�P�Q�Q�R�R�S�S�T�T�U�U�V�V�j
���Ă킩��悤�ɁA����͂P�S�̃n�C���w�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�̌`�ɂȂ��Ă��܂���B
���́u�P�P�v�u�Q�Q�v�u�R�R�v�u�S�S�v�u�T�T�v�u�U�U�v�u�V�V�v�̂悤�ɂQ���̑g�ݍ��킹���A�w�`�[�g�C�c�x�Ƃ����܂��B
�����̂��Ƃ���A
�����_���@
�}�[�W�����ł́w�`�[�g�C�c�x�������́w�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�̌`�̂ǂ��炩�̌`�����悢�I�I
�ȉ��ɗ�������Ă����܂��B���Ƃ��A
�@![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�i�u�P�P�P�v�u�R�R�R�v�u�U�U�U�v�u�X�X�X�v�u�S�S�v�j
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�Q�Q�Q�v�u�R�R�R�v�u�T�T�T�v�u�V�V�V�v�u�P�P�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�R�R�R�v�u�R�R�R�v�u�Q�Q�Q�v�u�U�U�U�v�u�R�R�v
�Ȃǂ̂悤�ɁA�w�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�̌`�����邩�A
���邢�́A
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�V�V�v�u�W�W�v�u�P�P�v�u�R�R�v�u�Q�Q�v�u�X�X�v�u�S�S�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�R�R�v�u�Q�Q�v�u�R�R�v�u�U�U�v�u�V�V�v�u�S�S�v�u�P�P�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�X�X�v�u�R�R�v�u�S�S�v�u�T�T�v�u�P�P�v�u�W�W�v�u�V�V�v
�Ȃǂ̂悤�ɁA�w�`�[�g�C�c�x�̌`�����悢�̂ł��B
�܂��A![]()
![]()
![]() �u�Q�Q�Q�v�̂悤�ɁA�����c�͓��������łȂ��Ă����܂��܂���B
�u�Q�Q�Q�v�̂悤�ɁA�����c�͓��������łȂ��Ă����܂��܂���B
![]()
![]()
![]() �u�P�Q�R�v�@�@
�u�P�Q�R�v�@�@![]()
![]()
![]() �u�S�T�U�v�̂悤�ɂȂ����������ł��A�������̂����܂�A�ƌ��Ȃ��܂��B
�u�S�T�U�v�̂悤�ɂȂ����������ł��A�������̂����܂�A�ƌ��Ȃ��܂��B
���Ƃ��A
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�P�Q�R�v�u�Q�R�S�v�u�U�V�W�v�u�T�U�V�v�u�S�S�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�S�T�U�v�u�Q�R�S�v�u�V�W�X�v�u�P�Q�R�v�u�T�T�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�Q�R�S�v�u�R�S�T�v�u�U�V�W�v�u�S�T�U�v�u�X�X�v
�̂悤�Ȍ`�ł����Ă��悢�̂ł��B
�ł�����A�v����Ƀ}�[�W�����́w�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�̌`������悢�̂ł�����A
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�P�P�P�v�u�Q�Q�Q�v�u�P�Q�R�v�u�S�T�U�v�u�W�W�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�T�T�T�v�u�S�T�U�v�u�V�W�X�v�u�R�S�T�v�u�S�S�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�P�Q�R�v�u�R�S�T�v�u�U�V�W�v�u�Q�Q�Q�v�u�T�T�v
�̂悤�Ȍ`�ł��悢�̂ł��B
�������A
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�P�Q�R�v�u�������v�u�T�T�T�v�u�Q�R�S�v�u�R�R�v
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
�@�u�S�S�S�v�u��ᢁv�u�Q�R�S�v�u�V�W�X�v�u�����v
�̂悤�Ȍ`�ł����܂��܂���B
�i���AᢁA���A�̂��Ƃ��u���n�C�v�Ƃ����܂��B�j
�i�P�A�U�A�X�A���̂��Ƃ��u���n�C�v�Ƃ����܂��B�j
![]() ���_
���_
�ȏ�̂��Ƃ���A�}�[�W�����́w�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�w�`�[�g�C�c�x�̂ǂ��炩�`�����肳������悢�̂ł��I�I
�{���ɁA���ꂳ���m���Ă���A�}�[�W������ł��Ƃ��ł��܂��B
(�� �A�^�}�̂��Ƃ𐝓��i�W�����g�E�j�ƌ����܂��B�j
���@�͂��B�Ƃ肠�����́A����ł��Ȃ��͂����}�[�W������ł��Ƃ��ł��܂���B
����ł́A���ۂɖ����Q�[���T�C�g�őł��Ă݂܂��傤�B�ׂ������[���͌�ɂ��āA�Ƃ肠�����l�b�g�őł��Ă݂܂��傤�`�B�ׂ������[�����ɕ���������A�܂��͑ł����ق��������͂����Ƒ����ł��傤�B
�i�u�S�����c�{�P�W�����g�E�v���ӎ����Ă���Ă݂Ă��������B���ꂾ���ӎ����Ă���ΑłĂ܂��̂ŐS�z���p�ł��B�O�O�j
�ȉ��ɖ����̃T�C�g�ւ̃����N��\���Ă����܂��B�i�Ǘ��l���悭�����őł��Ă��܂��B�j
���@���A���������I�I�@�Ō�Ɉ���������Ă����܂����A
�W�W�W�̂悤�ȃR�[�c�𑵂�������A�S�T�U�̂悤�ȃW�����c�����낦��ق����͂邩�Ƀ��N�I�I�I
�ł��̂ŁA����͈ӎ����đł��Ă݂Ă��������ˁB���S�҂ł��ƂW�W�W�̂悤�ȃR�[�c���ǂ����Ă����낦�����Ȃ�܂����A����Ȃ̖ő��ɂ��낢�܂����B�S�T�U�̂悤�ȃW�����c�����낦��悤�ɂ��Ă��������ˁB�i�ڂ����́A�ȉ��́u�R�[�q�[�u���C�N�v�ɏ����Ă����܂����̂ŁA�ǂ�łˁj
����ł́A�撣���Ă��������B������
�����i����܁j |
ID�ŗF�B�ǂ����őΐ���\�ł����A ��������邱�Ƃ��\�I�I |
|
�`�R�[�q�[�u���C�N�`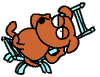
�����āA���̂R�S��ނ��ꂼ��S��������܂��̂ŁA �v�́A�S���ŁA�R�S�~�S���P�R�U���@���邱�ƂɂȂ�܂��B ����ł́A�P�������āA�����Ȃ��̎茳�� ����ƁA�c��P�R�T���̔v�̒��� ���ɔv�������� ���l�ɁA���̎��ɔv�������� �ȏ�̂��Ƃ��A�茳�� ���� ���̎��� �]���āA�A�����Ĉ�C�� (3/135)�~(2/134)��0.0003316 �܂�A���悻�O�D�O�R���ŁA���炭��ςł��邱�Ƃ��킩��܂��ˁB ��L�́A �������A����́A ���̂悤�ɍl����ƁA ����āA���_�́A �i�R�����g�j �����̂��Ƃ��l���A���ۂ̃}�[�W�����ł́A |
 �s���t�肪��{ �s���t�肪��{��̃R�[�q�[�u���C�N�ł��G��܂������A��ʂɁA�R�[�c���������A�W�����c�����ق������₷�����Ƃ��킩��܂����ˁB �W�����c���t���ɐ���������́A�ȉ��̂悤�ȁu�s���t�v�ƌĂ�����ł��B ��v�ȊO�œ����ɍ��A�S�g�Ƃ��W�����c�i�P�Q�R�ȂǁA���Ԃɕ���ł��邱�ƁB�j�ŁA���ʑ҂��B �܂��́A�s���t���_�����Ƃ��l���܂��傤�B���̍ہA�ł��X�s�[�h�̂���ł����͂ǂ̂悤�ɑłĂ悢�̂��H�\���I�Ŗ��ʂ̂Ȃ��ł������l����ׂ��ł��B �̂�т肵�Ă��ẮA���Ƃɐ�ɏオ���Ă��܂��܂��B�����̓X�s�[�h�����ł��̂ŁA�����ɔ\���I�ɏオ��܂Ŏ����Ă����邩�A���̃X�s�[�h���ƂĂ��d�v�ɂȂ��Ă��܂��B �܂��A�S�`���S�`�����Ă��Ă킩��Â炢�Ƃ��́A�S�����c�P�W�����g�E����ɍl���đł��悤�ɂ���ƁA�ł��₷���ł��B�S�����c�P�W�����g�E�ӎ����A����Ɍ����đł悤�ȃC���[�W�ł��B ���ꂪ���̒��ɂ���A�T�����c�ɂȂ肻���ȂƂ��A�̂Ă�n�C�̖ڐ������炩���ߗ��ĂĂ������Ƃ��ł��܂��ˁB �܂��A�����ŁA
�A�����̑匴���E�s���t������Ƃ��̑匴���ł����A �y���`�����҂������J���`�����҂��A�J���`�����҂����������������҂���D�悳����Ƃ������Ƃł��B �y���`�������J���`���������������� �ł��B �܂��A���Ղ́A������L�����đł��悤�ɂ���Ƃ悢�ł��傤�B �n�C�̎�����Ȃ�ׂ���������悤�ɑł̂ł��B ���Ƃ��A���Ղ� �Ƃ���A�܂��肪�قƂ�Ǒ����Ă��Ȃ����́A �������A����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A�ق��Ɏ��v�Ȃǂ̂����ƕs�v�Ȕv���������Ă���Ԃ� �܂��A���� �̂U���̒�����P���̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��́A���R�A �ł́A���� �̒�����P���̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��́A�ǂ�����悢�ł��傤���H �J���`���������������� �̃��[���ɏ]���A�̂Ă�̂� �̂Ă�ׂ��́A��͂� �܂��A ���̏ꍇ�A �����爫�`�̃y���`�����҂� |
|||||||||
�ǂ���ł������H�����ł͂���܂���B�����́A �Ȃ��Ȃ�A�����A ����A ���̂悤�ɍl���A |
 �V���{�C��ł��X�s�[�h�d���ŁI�I �V���{�C��ł��X�s�[�h�d���ŁI�I�V���{�C��ł�����܂��傤�B����A�V���{�C��Ƃ��������A�Ƃɂ����X�s�[�h�d���̑ł���������̂ł��B �V���{�C��ŏオ��ƁA���肩��u�[�C���O�����܂��ˁB����Ȃ��͖̂����ł��B �������������_���Ă���̂ɃV���{�C��ŏオ���āA�������オ��Ȃ�����A�u�[�C���O�����Ă��邾���ł��B����Ȃ��̂Ɏ����X���A�e�Ɍ������Ƃ��Ă�����A����Ɏ����̂���������邾���ł��B �X�s�[�h�d���̑ł������������ʁA�V���{�C��ɂȂ��Ă��܂��ꍇ������܂����A����ł悢�̂ł��B �Ȃ��Ȃ�A�X�s�[�h���d�����������������邱�Ƃɂ���āA�R�l�̑�����~�߂邱�Ƃ��ł��邩��ł��B�R�l�̑�����~�߂邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ́A�������_���Ă����玩�����}�C�i�X�ł����������A�����������ł��v���X�ɂȂ�̂ł��B�}�C�i�X���v���X�ɂȂ�ƍl������̌��ʂ��ǂꂾ���傫�����킩��܂��B����ɁA������Ō�ɃE�}���t���܂��B����Ƀ��[�`�������Ă����Η��h���A�ꔭ�̉\�����o�Ă���̂ŁA�V���{�肪���шȏ�ɂȂ邱�Ƃ�������܂��B����ɁA���[�`��������A����R�l�������ꍇ�����Ȃ�����܂���B �X�s�[�h�d���̑ł������ǂꂾ���L�����킩��ł��傤�B �X�s�[�h�d���̑ł����́A�U���ׂ̈̑ł����Ƃ��������A�h��ׂ̈̑ł����Ƃ��ĂƂ炦��悢�̂ł��B ���肩�猾�킹��ƁA �u����ȃV���{�C��A�A�z���ȁB�����ƍ������ďオ������̂ɔn������˂��́B�v �ƌ�����킯�ł����A �������ďオ���Ă�����A�t�ɂR�l�̑���̒N���ɐ�ɂ������Ă��܂��̂����� �ł��B ����ɂ��������Ԃ��ƁA �u�オ���˂���v �ƌ����܂����A�����Ȃ�Ă���܂���ˁB����Ȉӌ��̑��肱���A�{���̔n���Ȃ̂ł��B �����Ƃ����̂́A�ǂ�Ȃɑł��肪�C�������āA�������o���A���_�̍�������撣���č�낤�Ƃ��Ă��A�v�ƈ����v�����̂悤�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł�����A�撣�����Ƃ���Ŗ��ʂȂ̂ł��B ����Ȗ��ʂȂ��Ƃ��������A���R�Ɉ��������v�����悤�ȑf���Ȃ�����������ׂ��ł��B ������Ƃ����̂͑_���ďo�����̂ł͂Ȃ��A���R�̑ł����̗���̒��Ŗ����Ȃ��o���ׂ������Ȃ̂ł��B �u�������_���ďo���v�ƌ����l�����܂����A���������l�قǂ܂��������ア���̂ł��B �ア�����ɁA���l�ɃA�h�o�C�X�����ł��ˁB���������n���͋C�ɂ��Ȃ����Ƃł��B ����������悤�Ǝv�������ŁA���ۂɍ����ł��āA�������オ���悤�Ȃ�A�N����J���܂���B �����Ȃ�Ȃ��悤�ɔv������ł���킯�ł�����A������C���ƍ����Ŋ撣���Ă��A���ʂȂ̂ł��B �X�s�[�h�d���̑ł����͂ƂĂ��L���ł��B |
�������P�ʂ��ƁA�V���{�C��ł������܂���ˁB �܂��A���[�`�������Ƀe���p�C���Ă����A�V���{����ł��オ���Ă��܂��A�����܂��B ���邢�́A�ꍇ�ɂ���ẮA�e���p�C���Ă��Ă����[�`���������ɁA���ł�����邱�Ƃ��o����悤�ɂ��Ă������肵�܂��B ���́A���̍l�����́A�������P�ʂł͂Ȃ��Ƃ��ɂł�������킯�ł��B �������P�ʂ̂Ƃ��Ƃ����łȂ��Ƃ��ŋɒ[�ɑł������ς��Ƃ����̂͂������Șb���Ǝv���܂��H ��ɂǂ�ȂƂ��ł��A�\���I�ȑł��������Ă���A�ǂ�Ȏ��ł�������x�����������ɂȂ�͂��ł��B ���������l�����Ȃ��������������Ԃ����Ƃ��ă{�����������̂ł��B �オ��Ȃ��ǂ͑S�̂�3/4������킯�ł�����A�オ�邱�Ƃ�������邱�Ƃ̂ق����͂邩�ɏd�v�ł��B �����A�������P�ʂł͂Ȃ��Ƃ��ł��A�傫�Ȏ������Ĉꔭ�t�]���悤�Ƃ���ƁA�t�Ƀ{����������ꍇ���قƂ�ǂł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B �������S�ʂȂ�A�R�ʂɁA�R�ʂȂ�Q�ʂɁB����������Ȃ�A��C�ɋt�]���悤�Ƃ����A�����ł悢�̂ł��B�����Ď��ۂɂ͂��ꂵ���o���Ȃ��̂ł�����B ���������Ƃ����ʂ��ς��Ȃ��Ă��A�V���{����ł��オ���Ƃ��͏オ���Ă����܂��傤�B �����ŁA �u�V���{����ŏオ���Ă����ʂ��ς��Ȃ��̂�����Ӗ��������ł͂Ȃ����B�v �ƍl����̂ł͂Ȃ��A �u�����ŏオ��Ȃ�������A���Ƃɏオ���āA����Ɏ����̃}�C�i�X�������ĂƂ�ł��Ȃ����ɂȂ��Ă����B���`�オ���Ă����Ă悩�����B�v �ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��B �O�q�́A�X�s�[�h�d���̘b���v���o���Ă��������B �n�܂������_�łQ�T�O�O�O�_�A������P�ʂƂ��čl���Ă��������B���Ƃ͓����邾���B���Ƃ��V���{�C��ł��A���̂R�l��}���āA�������X�s�[�h�d���ŏオ���Ă����Ƃ���A��������ʂł��B����ɃE�}���t���܂��B���ƂɃ��L�g�����t���ꍇ������ł��傤�B |
���Ⴛ�̂Q��@�A�u�����o���邱�ƁB�v
�@�Ⴛ�̂P��Ō��Ă����悤�ɁA�}�[�W�����́w�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�̌`������悢�A�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B
�@�������A�w�����c�~�S�{�A�^�}�~�P�x�̌`�ɂ�
���u���̂Ɏ��Ԃ��Ԃ��������đ�ςȂ��́v�i������`�j�ƁA
���u�炭�ɍ��鎞�Ԃ̂�����Ȃ��ȒP�Ȃ��́v�i���ȒP�Ȍ`�j������܂��B
�����āA�u����`�v�͓_���������A�u�ȒP�Ȍ`�v�͓_�����Ⴂ�B�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����āA���́u�`�v�̂��Ƃ��u���v�Ƃ����܂��B�i�v����ɁA�u�`�v���u���v�j
�ł�����A�}�[�W�����ł́u����`�v�ł͂Ȃ��A�u������v�Ƃ����܂��B
���l�ɁA�u�ȒP�Ȍ`�v�ł͂Ȃ��A�u�ȒP�Ȗ��v�Ƃ����B
�Ƃ���ŁA�}�[�W�����ł́A�S�l�̂����ŏI�I�ɓ_������ԍ��������l���P�ʁB���l�ɂQ�ʁA�R�ʁA�S�ʁA�ƂȂ�܂��B��ԓ_���̍����l�́A���ꂾ����������������炦�邵�A�t�ɁA��ԓ_���̒Ⴂ�l�́A�����������x����Ȃ���Ȃ�܂���B
�����Ȃ�ƁA���R�A�_���̍������i��������j��_���̒Ⴂ���i���ȒP�Ȗ��j�����Ȃ̂��A�m���Ă������ق����L���ɂȂ�܂��B�i�m��Ȃ��Ă��}�[�W�����͂ł��邪�B�j�����āA���̖��͑S�����R�R�������܂��B�ȉ��ɋ����Ă����̂��ËL���Ă��������B�i�������A���ʂ͂˂���͂��܂��ňËL������̂ł͂Ȃ��A������x�͂��Ȃ���o���Ă������̂ł��B�j
�i���Ȃ݂��u���v�Ƃ́u���l�̃n�C��������Ă��邱�Ɓv�ł��B�j�i�܂��A�u���i���N�j�v�Ƃ́u�P�ʁv�̎����Ǝv���Ă��������B�j
| �� | ���O | ���� |
| �P �� |
���[�` | �e���p�C�i���ƈ�łł�������Ƃ�����ԁB�j������u���[�`�I�v�Ɛ錾���悤�B |
| �c�� | �����[���c���i�����ň����Ď����Ă��邱�ƁB�j�����������悢�B | |
| ���n�C | ||
| �s���t �i�����[�����j |
��v�ȊO�œ����ɍ��A�S�g�Ƃ��W�����c�i�P�Q�R�ȂǁA���Ԃɕ���ł��邱�ƁB�j�ŁA���ʑ҂��B |
|
| �^�����I | �P�E�X�E���v�������Ă��Ȃ��B �i�N�C�^���i���l�̔v��������Ă��邱�ƂŃ^�����I�����邱�ƁB�j���P���j |
|
| �C�[�C�R�E �i�����[�����j |
������ނŁA�����������Q�g���B |
|
| �n�C�e�C | �Ō�̃n�C�Ńc���܂��̓����i���l�̎̂Ă��v�ŏオ���錾���邱�ƁB�j�ł�����ƂP���B | |
| �����V�����J�C�z�E | �J���i�S�������v���茳�ɂ���ꍇ�j�����āA�����V�����v�Ńc��������B | |
| �`�����J�� | ����́u�lj��̃J���v�Ń����i�J���������l�̂P�l�����j | |
| �Q �� |
�O�F�i�H��������P���j | �����Y�E�s���Y�E�\�[�Y�œ�������������B |
| ��C�ʊсi�H��������P���j | ������ނłP�`�X�����낦��B |
|
| �g�C�g�C | �A�^�}�ȊO�̓|�����A���R�̂�����B�i�|�������Ă��H��������Ȃ��B�j |
|
| �`�[�g�C�c�i�����[�����j | ||
| �_�u���[ | �|���E�`�[�E�J���̂Ȃ��Ƃ��A�u���̂Ĕv�v�Ń��[�`��錾����B | |
| �`�����^�i�H��������P���j | �P�E�X�v�����v�̊W�����g�ݍ��킹���� |
|
| �O�A���R | �A���R���R�g |
|
| �O�F���|�� | ||
| �O�J���c | �R�g�̃J�������i�A���J���ł��~���J���ł������B�j �i�A���J���Ƃ͎��������łS�����邱�ƂŁA�~���J���Ƃ͑��l�̔v���ꖇ������Ă��ĂS�����邱�Ɓj |
|
| �z�����E�g�E | �P�E�X�v�Ǝ��v�ɂ��オ��B�z�����E�g�C�g�C�i�S���j�ƃz�����E�`�[�g�C�c�i�Q���j������B |
|
| �R�� | �z���C�c�i�H��������Q���j | ���v�ƂP��ނ̐����v�ɂ�邠����B |
| ���`�����i�H��������Q���j | �P�E�X�̃A�^�}�ƃ|���܂��̓A���R�ŁA�����͂P�Q�R���V�W�X |
|
| �������y�C�R�E�i�����[�����j | �C�[�[�R�[�Q�g���B�i�`�[�g�C�c�Ƃ̓_�u���Đ����Ă͂����Ȃ��j |
|
| �S �� |
���O�� | ���E���E���̂����Q��ނ��R���B�c��̂P��ނ��Q���B�i���v�̂Q���͊܂܂�Ă���j |
| �z�����E�E�g�C�g�C | �P�E�X�v�Ǝ��v�ɂ��g�C�g�C |
|
| �z�����E�E�`�[�g�C�c | �P�E�X�v�Ǝ��v�ɂ��`�[�g�C�c |
|
| �U �� |
�`���C�c�i�H��������T���j | ���ނ̐����v�����ɂ�邠����B |
| �� �� |
���m���o�i�����[�����j | �P�R��ނ̂P�E�X�v�Ǝ��n�C�����ׂĂ��낦�A�ǂꂩ���A�^�} |
| �l�A���R�i�����[�����j | �S�̃A���R�B |
|
| ��O�� | ���E���E�����R�܂������낦��B�i�|���ł��A���R�ł������j |
|
| ��l��E���l�� | ���v�����ׂĂR�������낦��Ƒ�l��C��g���A�^�}���Ə��l��i��������j |
|
| �V�a | �e���z�v�i�P�S���j���ɏオ���Ă����B | |
| ����F | ���v�����̃g�C�g�C�܂��̓`�[�g�C�c |
|
| �Έ�F | �ΐF�̔v�����ō�邠���� |
|
| �`�����E�g�E | ||
| ��A�i�����[�����j | �P�E�X���R���ŁA�Q�`�W���P�����g���������[���̃`���C�c |
�i���P���̂��Ƃ��P�|���A�Q���̂��Ƃ��Q�|���A�R���̂��Ƃ��R�|���c�ȂǂƂ����ꍇ������܂��B�j
 �����p��W�i�K�{�ҁj �����p��W�i�K�{�ҁj�������I�i�t�[���j�Ƃ́A���̃v���C���[�̑Ŕv���擾���邱�Ƃɂ��ʎq�����������邱�ƁB�|���A�`�[�A�J���i�喾�ȁj��3��ނ�����B���A�A�N���A�@���ȂǂƂ������B �|���c��v�̒��ɑΎq�i����̔v2���j�����݂��A���̃v���C���[������Ɠ����v��Ŕv�����Ƃ��A�����3���̔v���ЂƂ̍��q�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B �`�[�c��v�̒��ɓ��q�����݂���ꍇ�A��Ɓi�����̃v���C���[�j�̑Ŕv���擾���ď��q�����������邱�Ƃ��ł���B �h���c�a�������Ƃ��ɓ��_�̉��Z�ɂȂ������̔v�̂��Ƃ������B�P���Ɠ��������̉��l�����邪�h�������ł͏オ��Ȃ��B ���q�i�R�[�c�j�c�����v��3���W�߂�1�g�̂��ƁB ���q�i�V�����c�j�c�U�V�W�̂悤�ɂR�����v�B ���v�i�c�[�p�C�j�c���쐼�k�������̎��v�̂��ƁB ���́i���E�c�[���[�j �c�R����v�������Ă��邱�ƁB �a���i�z�[���j�c������̂��ƁB �U���i�t���e���j�c���������łɎ̂Ă��v�ŏオ�邱�ƁB�t���e���ł͂�����Ȃ��B ���I��v�i���I�`���[�p�C�j �c�P�E�X�E���v�̂��ƁB �Ă��� �c�����������Ă��Ȃ��l�ɂ̓y�i���e�B�Ƃ��ē_�����������B �������h�a �c���l�̎̂Ă��v�ł����邱�ƁB ��t�� �c���̂Ȃ��܂��i�߁A���Ƃ���������邱�ƁB ���ǁi��イ���傭�j�c�S�l����������ꂸ�A����邱�ƁB ���h���E�����ܔv �c���[�`�������̂��オ�����Ƃ��ɁA�h���\���v�̉��ɂ���v���h�������ƂȂ�B����𗠃h���Ƃ����B���h���͏オ��܂Ō��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �ȁi�J���j�c�Ȏq�i�J���c�j����邽�߂̍s�ׂ̂��Ƃ������B �Ȏq�i�J���c�j�c�Ȃ����ē����v��4��1�g�ɂ��ĎN�������̂̂��ƁB���q�Ƃ��Ă�������B �ÞȎq�i�A���J���c�j�c���l�̔v������ƂȂ��A���������̔v�łS����Ȃ������́B ���ȁi�~���J���j�c���l�̔v������Ƃō�����Ȏq�̂��ƁB�喾�ȁi�_�C�~���J���j�Ɖ��ȁi�J�J���j������B���Ȃ͏����ȁi�V���E�~���J���j�Ƃ������A�|�����Ă���R���Ɍォ�玩���̔v�����������́B ������i�C�[�V�����e���j�c�e���p�C�܂ł��ƂP�̏�Ԃ̂��ƁB ���v�i�e���p�C�j�c���ƂP�v�ŏオ����Ԃ̂��ƁB ���S�v�E���v�i�A���p�C�j�c��Ɏ̂ĂĂ����Ƃɕ��e����i�����ƌ����Ă��܂��j�댯�̂Ȃ��v�̂��ƁB ��|����i�C�[�t�@������j �c�����P�|�ȏ�Ȃ��Ƃ�����Ȃ����ƁB �I�[���X�i���X�O�E�僉�X�j �c���X�g�P�Q�[���̂��ƁB�Ō��1�ǁB �e�i����j�c�e�͓��Ɓi�g���`���j�Ƃ��Ă�e���甽���v���ɓ�Ɓi�i���`���j�A���Ɓi�V���[�`���j�A�k�Ɓi�y�[�`���j�ƌĂсA������q�ƌ����B �e�̓��_�͎q�̓��_��1.5�{�B �܂��A�����̍����̃v���C���[����Ɓi�J�~�`���j�A�E���̃v���C���[�����Ɓi�V���`���j�A�����Đ��ʂ̃v���C���[��Ζʁi�g�C�����j�Ƃ����B�܂��A�����ȊO�̃v���C���[�̂��đ��Ɓi�^�[�`���j�Ƃ����B ���v�i�����͂��E�t�@���p�C�j�c���v�̂����A���i�g���j�A��i�i���j�A���i�V���[�j�A�k�i�y�[�j��4��ނ̔v�̑��́B�l���v�i�X�[�t�H���p�C�j�Ƃ������B ������ �c���l�̔v������ƂŁA�����̎���̖|���������邱�ƁB �f���I��i�^�����I�j�c��㎚�v����؎g�킸�ɐ��v��2�`8�����Ŏ�v���������������́B���Ƃ̔v����Ă���ꍇ���N�C�^���Ƃ����B �E�}�c�Ō�̓��_�v�Z�̂܂Ƃ߂̎��ɂP���A�Q���A�R���A�S�������ꂼ�ꂩ�瓾���链�_�̂��ƁB 5-10 �S�b�g�[�i4�ʂ�1�ʂ�1���_�A3�ʂ�2�ʂ�5,000�_�����j 10-20 �����c�[�i���A2���_��1���_�j 10-30 �����X���[�i���A3���_��1���_�j �Ȃǂ�����B |
���Ⴛ�̂R��@�B�u���_�v�Z���ł��邱�Ɓv�i�������_�v�Z�@�j
�����̌v�Z
���Ƃ͕ʂɁA���������Ƃ��ɁA�_�����t�����̂�����܂��B�ȉ��̕\�����Ă��������B
�����̓_���̍��v���o�����Ƃ�"��"�̌v�Z�Ƃ����܂��B
| ���g�ݍ��킹�ɂ��_ | |||||||
| �g�ݍ��킹�̎�� | �^�����I�v | �P�E�X�v�Ǝ��v | |||||
| �A�^�} | �O�_ |
��v�݂̂Q�_ |
|||||
| �����v���R�� | �|�� | �Q�_ |
|||||
| �A���R | �S�_ |
�W�_ |
|||||
| �J�� | �~���J�� | �W�_ |
|
||||
| �A���J�� | �P�U�_ |
�R�Q�_ |
|||||
| ����������ɂ��_ | |||||
| �e���p�C�̌` | �e���p�C�̗� | ������v | ���� | �c�� | |
| ���ʑ҂� | �O�_ | �Q�_ | |||
| �J���`�����҂� | �Q�_ | �S�_ | |||
| �y���`�����҂� | �Q�_ | �S�_ | |||
| �V�����|���҂� | �^�����I�v | �O�_ | �Q�_ | ||
| �P�E�X�v�Ǝ��v | �O�_ | �Q�_ | |||
| �A�^�}�҂� | �^�����I�v | �Q�_ | �S�_ | ||
| �P�E�X�v�Ǝ��v | �Q�_ | �S�_ | |||
�����_�v�Z����@�i�����|�C���g���b�X���j
�E���ʊ�{�_�͂Q�O�_�X�^�[�g
�E�c����ƂQ�_
�i�������ł̃c���Ƃ́A���Ƃ��Ẵc���ł͂Ȃ��A���Ƃ��Ȃ��Ă��Ă��A���Ƃ��Ẵc���͂��Ȃ����A
���Ƃ��Ẵc���͂��Ƃ����Ӗ��̃c���B�܂肠������ɂ��c���ŁA���Ƃ��Ẵc���ł͂Ȃ��B�j
�E�����[���łȂ��s���t�n�����͂Q�O���P���ƂȂ邪�A����Ȃ̂Ȃ�����R�O���Ƃ��A�P�O�O�O�_�B�i���Ƃ��N�C�^���̂݁B�j
�E�����[���łȂ��s���t�n�c���́A�c���̂Q�_�����̂łQ�Q�_�B
�E�����́A�����[���Ȃ�v���X�P�O�_�B�i�Q�O�_�X�^�[�g�ŁB�j
�@�@�@�@�@�@�H���Ă���Ȃ�v���X�O�_�B�i�Q�O�_�X�^�[�g�ŁB�j
�E�c���͂Q�_���B��O�̓s���t�̃����[���s���t�c���̂݁B
�E�q�̃c���A�K����1/4 + 1/4 + 1/2
�i�@�����[���s���t�c���Ȃ�Q�O���B���̃s���t�n�i�����E�c���j�Ȃ�R�O���B�j
��
�A����ȊO�͂Q�O������X�^�[�g�B
��
�B�c�����������B
�i�����Ȃ�A�{�P�O�_or�{�O�_�̂Q�ʂ�B�c���Ȃ�A�Q�_�B�ior�����[�����a�c���Ȃ�v���X�O�_�j
��
�C�҂��͈ꖇ���H
��
�D�A�^�}�͖�v���H
��
�E�A���R�i�S�_��j�A�|���i�Q�_��j�A�J���i�P�U�_��j�́H
�i�������[���s���t�c���͗�O�B�j
�i���P���Q�O���́A�P���R�O���Ƃ���B�j
���_�v�Z���ʓ|���I�Ƃ����l�͑����B�����ŁA���Ǘ��l���A��G�c�ȓ��_�v�Z���@���Љ�܂��B �i�P�j�����[���s���t�c�����Q�O�� �i�Q�j�u�����[���s���t�c���v�ȊO�́A�u���a�v�y�сA�u���a�n�v�͂��ׂĂR�O�� �iex. �����[�����a�݂̂̃������R�O��)(�������[���̃����̂P�O�����t���ā{�P�O���łR�O���j �iex.�@�s���t�n�̃c�����R�O��)( �i���u�s���t�n�v�Ƃ́A�S�̏��q�ƂP�̐����ŏo���Ă����v�̂��Ƃ������B���Ƃ��A���҂��̕��a�ȂǁB�j�i���҂��ŏオ�����̂Ȃ�A���҂��̂Q�������ĂQ�Q�����R�O���j �i�R�j��{�͂ǂ���R�O�� �i�S�j�����[���̎�ŁA�������S�O���i�������A�s���t�n�ł͂Ȃ��B�j�i�������[���������P�O���A��{�_���Q�O���A����ō��v�R�O�������A�s���t�n�ł͂Ȃ��̂ŁA���q�ł͂Ȃ����̂�����̂ł��_���Z����A�R�O�{���_���A�S�O���i�ȏ�j�j �Ƃ��Ċo���Ă����A���Ƃ́A �i�R�j�i�S�j�ɂ��Ắu�J���v������ΌJ��オ��m���A �u�P�E�X���v�̃A���R�v�������āA���ɉ����҂������������A�A�^�}���P�E�X���v��������A�_���̕t�����̂��P�ł�����ΌJ��オ��m���B �Ɗo���悤�B�i�����Ȃ����ł͂Ȃ��ł����c�B�����ɂ��̂Ȃ�A�i�R�j�i�S�j��������������ƃA�^�}�A�A���R�A�|���A�J���Ōv�Z����K�v������B�j |
���āA�s���̂Q�t�Łu���v���w�K���܂����B�����āA�s���̂R�t�Łu���v���w�K���܂����B
�����u���v�Ɓu���v�����킹�ē��_�v�Z�����܂��B
�ȉ��ɏ�����Ă���_�����A���������Ƃ��̓_���ɂȂ�܂��B
�����_�v�Z�����\
| �e �� �A �K �� |
�� | �P�| | �Q�| | �R�| | �S�| | �T�| |
| �Q�O[�s���t�E�c��] | �w | (700) | (1300) | (2600) | ���� | |
| �Q�T[�`�[�g�C�c] | �w | �Q�S�O�O | �S�W�O�O (1600) |
�X�U�O�O (3200) |
���� | |
| �R�O | �P�T�O�O (500) |
�Q�X�O�O (1000) |
�T�W�O�O (2000) |
�P�P�U�O�O (3900) |
���� | |
| �S�O | �Q�O�O�O (700) |
�R�X�O�O (1300) |
�V�V�O�O (2600) |
���� | ���� | |
| �T�O | �Q�S�O�O (800) |
�S�W�O�O (1500) |
�X�U�O�O (3200) |
���� | ���� | |
| �U�O | �Q�X�O�O (1000) |
�T�W�O�O (2000) |
�P�P�U�O�O (3900) |
���� | ���� | |
| �V�O | �R�S�O�O (1200) |
�U�W�O�O (2300) |
���� | ���� | ���� | |
| �W�O | �R�X�O�O (1300) |
�V�V�O�O (2600) |
���� | ���� | ���� |
( )���̓c���A�K���̂Ƃ��́i�P�l���j�̎x����
| �q �� �A �K �� |
�� | �P�| | �Q�| | �R�| | �S�| | �T�| |
| �Q�O[�s���t�E�c��] | �w | (700�E400) | (1300�E700) | (2600�E1300) | ���� | |
| �Q�T[�`�[�g�C�c] | �w | �P�U�O�O | �R�Q�O�O (1600�E800) |
�U�S�O�O (3200�E1300) |
���� | |
| �R�O | �P�O�O�O (500�E300) |
�Q�O�O�O (1000�E500) |
�R�X�O�O (2000�E1000) |
�V�V�O�O (3900�E2000) |
���� | |
| �S�O | �P�R�O�O (700�E400) |
�Q�U�O�O (1300�E700) |
�T�Q�O�O (2600�E1300) |
���� | ���� | |
| �T�O | �P�U�O�O (800�E400) |
�R�Q�O�O (1600�E800) |
�U�S�O�O (3200�E1600) |
���� | ���� | |
| �U�O | �Q�O�O�O (1000�E500) |
�R�X�O�O (2000�E1000) |
�V�V�O�O (3900�E2000) |
���� | ���� | |
| �V�O | �Q�R�O�O (1200�E600) |
�S�T�O�O (2300�E1200) |
���� | ���� | ���� | |
| �W�O | �Q�U�O�O (1300�E700) |
�T�Q�O�O (2600�E1300) |
���� | ���� | ���� |
( �@)���̓c���A�K���̂Ƃ��́i�e�E�q�j�̎x����
�y���шȏ�̓_���z
�n�l���i�U�E�V�|�j�c�e�P�W�O�O�O�E�q�P�Q�O�O�O
�{���i�W�E�X�E�P�O�|�j�c�e�Q�S�O�O�O�E�q�P�U�O�O�O
�R�{���i�P�P�|�ȏ�j�c�e�R�U�O�O�O�E�q�Q�S�O�O�O
�i�|���W�Ȃ��j�c�e�S�W�O�O�O�E�q�R�Q�O�O�O
�ł́A�����܂ł̒m���܂��āA���_�v�Z�̗��K�����Ă݂܂��傤�B
�͂��߂̂����́A��L�̕\����������Ȃ������Ă��\���܂���B
 ���_�v�Z��{�T�p�^�[�� ���_�v�Z��{�T�p�^�[���� ���̓_���v�Z�����Ȃ����B
�i����j �Q�O���i�P�|�j �i����j �i�P�j�����[���s���t�c�����Q�O���ł����ˁB �i����ɏڂ�������j �y���z��{�_���Q�O���@�݂̂ƂȂ�܂��B �y���z���a�݂̂̂P�|�ŁA700�E1300�_�B
�i�����j �S�O���i�R�|�j �i����j �i�S�j�����[���̎�ŁA�����i���������a�n�ł͂Ȃ��j���S�O���ł����ˁB �i����ɏڂ�������j �y���z �J���`�����҂����Q�� �����[���������P�O�� ��{�_���Q�O�� ���v�R�Q���ŌJ��グ�S�O���ł��B �y���z �s���t�i�P�|�j�A��C�ʊсi�Q�|�j�ŁA���v�R�|�ł��B �e�̂R�|��7700�_�B
�i�����j �R�O���i�P�|�j �i����j �i�R�j��{�͂ǂ���R�O���ł����ˁB �i����ɏڂ�������j �y���z ��{�_���Q�O�� �^�����I�Í����S�� �^�����I�������Q�� ���v�Q�U���ŁA��グ�R�O�� �y���z �^�����I�̂݁B�P�O�O�O�_�B
�i�����j �R�O���i�R�|�j �i����j �i�Q�j�u�����[���s���t�c���v�ȊO�́A�u���a�v�y�сA�u���a�n�v�͂��ׂĂR�O���ł����ˁB �i����ɏڂ�������j �y���z ��{�_���Q�O�� �����[���������P�O�� ���v�R�O�� �y���z ���a�i�P�|�j �h���Q ���v�R�|
�i�����j �Q�T���i�R�|�j �i����j �`�[�g�C�c�͂Q�T���ƌ��܂��Ă��܂��B �i����ɏڂ�������j ���Ύq���Q�T�� �i���Ӂj�`�[�g�C�c�͂Q�T���ƌ��܂��Ă���̂ŁA�c�����Ă��c�����͕t���܂���B �_����1600�I�[���B �� ��{�͈ȏ�T�p�^�[���ł��ׂĂł��B ����ɏڂ������K�����������������������ցB |
 ���̌v�Z�A�����|�C���g���b�X�� ���̌v�Z�A�����|�C���g���b�X�� �u�J���`�����҂��v�Ƃ݂邩�A�u���ʑ҂��v�Ƃ݂邩�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B �����A�J���`�����҂��ƌ����ꍇ�A �܂�A�C�[�y�[�R�[�����Ƃ���Ȃ�A�J���`�����ƌ����ق�������������܂��B �������A���ʑ҂��ƌ����ꍇ�A �S�T�U�̎O�F�ɂȂ�܂��̂ŁA���͂������a�O�F�C�[�y�[�R�[��7700�_�ɂȂ�܂��B �i�� ���Ƀ^�����I�ł����Ă�}���K���ł����܂��B�j ���Ȃ݂ɁA �R�S�T��3�F�ł����A���ʑ҂��ł͂���܂���̂ŁA���a���t���܂���B �����ŃJ���`�����łƂ��ĎO�F�C�[�y�[�R�[��5200�_�ł��B �i�� ���l�ɁA�^�����I�Ȃ瓯�����}���K���ł����B) �܂��A ���a��������ΒP�R�łQ�������܂��B ���̍����ق��ł����āA�P�R�Ƃ��A�J���`�����̂ق��łƂ�ق����L���ł��B |
�ȏ�́s���̂P�`�R�t�܂ł������łȂ��Ƃ����܂��܂���B�W�����x�ł��ǂ��̂ŗ������Ă��������B
�K��������łĂ�悤�ɂȂ�܂��B�O�O
 |
�����ɂ��Ă̘b��͈ȉ����炨�肢���܂��B |
| �I�[�v���`���b�g�����E�}�[�W���� |
���s���̂S�t�i�}�i�[�ҁj
���}�i�[�P�@��Q�[�����n�߂�O�Ƀ��[�������߂悤��
�u�A���A���v��u�E�}�Ȃ��v�ȂǐF�X�ȃ��[��������܂����A�܂��A�Q�[�����n�߂�O�Ɍ��߂Ă����܂��傤�B
�I�[�v�����[�`�Ȃǂ̃��[�����͂��߂Ɍ��߂Ă����������悢�ł��傤�B�I�[�v�����[�`�͍̗p���Ȃ��Ŗ���������l�������悤�ł����A�M�����u���������߂邽�߂ɍ̗p���Ă���O���[�v������A�܂��܂��ł��B�����̎���̓_�����Ⴍ�A�������A�҂��������ďo�����ɂȂ��ꍇ�ɁA����ɃI�[�v�����[�`���n�߂�l�����܂����A����͂ǂ����Ƃ������܂��B���̐l���猾�킹��A�S�������������Ȃ̂�������͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ肻���ł����A����A���ł��B�܂��A�I�[�v�����[�`���̗p���邩���Ȃ����A���܂��Ă��Ȃ����_�Ȃ�A�v�����[�������ق����L���Ɣ��f�����ꍇ�A�����āA��Ԃ͂��߂ɃI�[�v�����[�`��錾����`�����X�������l���ł��L���ɂȂ�܂��B�����A����Ƃ͕ʂ̐l���I�[�v�����[�`�������ق����L���ȏ����߂ɗ����ꍇ�A�u�I�[�v�����[�`���Ă����H�v�ƕ����āA�ʖڂ��ƌ�����\�������邩��ł��B���̏ꍇ�A���i�̗F�l���m�ł̗͊W�ɂ���Ă��߂��邽�߁A�����̎��͂Ƃ͊W�Ȃ��ɁA���茠�̂�苭���l���L���ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�V�V�O�O�_���W�O�O�O�_�ɂ��邩�ǂ����ɂ��Ă��A�܂������������Ƃ������܂��B��Ԃ͂��߂ɂV�V�O�O�_�����������l���A���̎��_�ŁA�W�O�O�O�_�ɂ��悤�ƌ����A�������ɁA����ȍ~�̃Q�[���ł����̂R�l���W�O�O�O�_�ɂȂ�܂����A�������߂ɑ��̐l���V�V�O�O�_�����������Ȃ�A�V�V�O�O�_�̂܂܃Q�[�����i�s���邩������܂���B�������A����ł������͊F�����ł����A���ꂩ���̃Q�[���ł��W�O�O�O�_�i�܂��͂V�V�O�O�_�j�Ƃ����������[���ő�����Ȃ�A���̃Q�[���̉�������ɋ߂Â��߂Â��قǁA�����͌���Ȃ������ɋ߂Â��Ă����Ƃ�����̂ł����A���܂ɉ���Ė����������x�Ȃ�A��ԏ��߂ɂ��܂������̓��_�������Ȃ����l���L���ɂȂ��Ă��܂��ƌ����܂��B
�ɒ[�Șb�A���̃����o�[�����������������Ă����Ƃ��āA���̒��ŁA�I�[�v�����[�`������o�Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ�A���̃I�[�v�����[�`�����邱�Ƃ��A�^�ǂ��F�߂�ꂽ�l���ł��L���ɂȂ�܂��B
���}���̓_����_�u���̓A���Ȃ̂��A�g���v���ȏ���A���ł��̂��A�Ȃ��ł��̂��A�ȂǁA�Ƃɂ������ׂẴ��[���ɂ��āA���̂��Ƃ����Ă͂܂�܂��B��ԏ��߂ɋ��R�i���邢�͕K�R�j���̂悤�Ȏ���ɂȂ�A��ԏ��߂ɔF�߂�ꂽ�l���ł��L���ɂȂ�̂ł��B
�������I����Ă���A�P�ʂ̐l���ł������E�}�Ɍ��肷��Ƃ����̂��������Ƃł��B
�����͏����Ȗ����̎��͂ŏ����Ă����ʔ����̂ł�����A���߂Ƀ��[���͌��߂Ă����ׂ��ł��B
���}�i�[�Q�@�ᕉ�����炨���͂����ƕ����܂��傤��
�悭�g�����i���A�u���߂�A����������Ƒ҂��āB���Ƃŕ�������B�v�u�o�C�g��������K����������B�v�ƌ����ĉ����Ă����āA���ǂ͕���Ȃ����ł��B�܂��́A���肪�Y���̂�҂��܂��B���������l�ԂɌ����āA�������������ꍇ�ɐl���瓯������������ƌ������̂̂���܂��B�����ĉ������̂ɋ��܂ŕ����̂̓v���C�h�������Ȃ����Ă�[�̂��悭������C�������ł����A�l�ԂƂ��Ăǂ����Ǝv���܂��H�����͂��̏�ł�����ƕ����܂��傤�B
���}�i�[�R�@�ᕉ�����畉����F�߂悤��
�v���C�h�������͕̂�����܂����A�������̂������畉���͔F�߂��ق��������Ǝv���܂��B�܂��A���Ă��Ĕ��Ɍ��ꂵ���ł����A����������������܂��B�^�̂����ɂ�����A�̒��̂����ɂ�����A���܂�������c�͂����猩�ĂĂ��ɁX�����B�\�͂��Ⴂ�Ǝv��ꂽ���Ȃ��̂��A����Ƃ����������Ǝv��ꂽ���Ȃ��̂��m��܂��A����ŕ����Ă���ɂ�������炸�A�������_���������悭��낤�Ƃ�����A�l�̑ł����ɑ��āA���̑ł����͊Ԉ���Ă���Ƃ��A�����Ƃ��������ł��������Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂��Ƃ��c���ӂ��ɁA����Ȃ��Ƃ��茾���Ă��܂����A���������l�Ɍ����āA�ʼn��ʂł��B�����A�{���Ɏ����̑ł������������Ȃ�A����ł���ď��Ă�͂��Ȃ̂ł����A���ĂĂ��Ȃ��Ƃ��������ƁA�܂��܂��l�����̂ł��B���̐l�̌����Ă��鎖���A�����̏�ʎ҂̐l����݂�A�����̗��B�܂�A������O�̂��Ƃӂ��ɋ������Ă�����̂ł��B���̂��Ƃɖ{�l�͒m��Ȃ��Ǝv���ċC�Â��܂���B�����I�ɔ��f���āA��͂薃�����ʎ҂͍l�����A�����Ă��Ȃ������������ƌ����܂����A�t�ɁA��ʎ҂͉��ʎ҂ɔ�ׂ�ƁA���ʎ҂������Ă��Ȃ����_�������Ă���B��������ƌ����Ă��镔���������Ƃ����܂��B�����炱���A���ꂪ���ʂƂȂ��ĕ\��Ă���킯�ł�����A�����Ă���ɂ�������炸�A��������ʎ҂ɃA�h�o�C�X������̂͂��������ł��ˁB�������畉����F�߂܂��傤�B
���}�i�[�S�@��[�`���Ă��邩��Ƃ����āA���l�̃n�C�����Ȃ���
���[�`���Ă���A�ƌ����āA���l�̃n�C�����Ă͂����܂���B�{�l�Ɍ��킹��A�����͂����u�c����v�����Ȃ�����A���Ă����͂Ȃ����낤�A�Ƃ������Ƃł��傤���A��肠��܂��B��ɏo��̂ŁA���l�ɂ�܂��B���Ƃ��A���l�̃n�C���������ʁA�e���p���Ă��āA���ꂪ�s���Y�̃`���C�c�̎O�����҂��������Ƃ��܂��B������́A�s���Y����Ɏ̂Ă�ꂽ�Ƃ��́A���̐l�̊�F���ς��܂�����A���̂ł��B�u���̂��炢���v����v�Ƃ�����������܂��A���������o���܂��B�����ƂЂǂ��̂ɂȂ�ƁA�s���Y���������c���M������Ƃ��ɂȂ�ƁA���̐l�̊�����Ȃ���̂Ă�l�����܂��B�����o���o���ł��B����ɂЂǂ��l�ɂȂ�ƁA�u���Ԃˁ[�c�v���Ƃ����ăn�C���̂Ă܂��B
�����������Ƃ��N����̂ŁA���[�`���Ă��邩��Ƃ����āA���l�̃n�C�����Ă͂����܂���B
�l�@�ᖃ�����ł́A�ǂ��܂ŃE�\���������̂��H��
���̖��̂ǂ��ɋ��E���������̂��͔��ɓ�����ł��B�������̂��ƁA�u�������͂ǂ�ȃE�\�����Ă悢�v�ƃ��[���ꂵ�Ă��܂��A�����͊F�����Ȃ̂ŁA�S������܂߂��A�{���ɏ����Ȏ��͏����̖������ł��܂����A�����ɗl�X�Ȗ�肪�N�����Ă���ł��傤�B
��������A�t�Ɂu�������̃E�\�͐�ɂ����Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��Ă��A�u�e���p�C���Ă�H�v�ƕ����ꂽ���ɂ͉��Ɠ�������悢�̂ł��傤���B�u�E�\����������A����͔F�߂Ȃ��B�v�ȂǂƂ�����ꂩ�˂܂���B
�u�������ɃE�\��M����ق��������v�Ƃ��u�E�\�����ق��������v���ƁA������c�_�������Ƃ���ŁA���̂悤�ȓ����̂Ȃ������A�����猾���������Ƃ���ŁA�����ȂǏo��͂����Ȃ��̂ł��B
�����Ȃ�ƁA���ǁA�l�l�̃������̖��ɂȂ�܂����A�������A����ł́A�^�ɕ����Ƃ͌����܂���B
�u�������́A�S���A�����őłv�Ƃ������@������܂����A�F�l���m�ł��̂Ȃ�A����������ł��B
��������A�l�b�g�Ń`���b�g���I�t�ɂ��đΐ킵�āA��ł����̐��Z������Ƃ����̂��v�����܂��B�������A�c�O�Ȃ���A�u����������ł���ɂ��������ăp�\�R�����t���[�Y����m���������Ȃ�B�v�Ƃ����@��������܂��̂ł�����g���܂���B����������ƁA�����Ă���m���ƃp�\�R�����t���[�Y����m���͂Ȃ�����Ⴗ��̂ł�(��)�B�������A�p�\�R�����t���[�Y����m���́A���̎��_�ŏ����Ă��悤�������Ă��悤���A�W���Ȃ��͂��ł�����A����̓t���[�Y�����ƉR�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�ł��̂ŁA�t���[�Y�����畉���Ƃ���Ȃǂ̃��[�������߂Ă����Ƃ悢�ł��傤�B
�b��߂��܂����A�u�������͂ǂ�ȃE�\�����Ă��悢�v�ƁA���[�������߂�̂��A�ł��悢���@�̂悤�ȋC�����܂��B�����͊F�����ł����A�O�����āA�S�����u�E�\�����Ă���\��������v�Ƃ������Ƃ�m���Ă���킯�ł�����c
�������A��������x������܂��B�͂��߂ɂ��̂悤�Ƀ��[�������߂��Ƃ���ŁA�l�ԁA�Ђǂ��E�\�͂��Ȃ����̂ł��B���ł�����́A�ǂ�ȃE�\������Ȃ�A���ɓI�ɂ͖����Ȃǂł��܂���B������x�́A����̂��Ƃ��l���Ȃ��玩���̃Z���t���l���Ȃ��Ƃ����Ȃ�����ł��B
���Ƃ��A���ŁA�����{�点��悤�Ȃ��Ƃ��킴�ƌ����A�Ƃ����̂͋�����邱�Ƃł͂���܂��A�u�����������[�����v�Ƃ������Ƃ���ŁA�߂��Ⴍ����ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA���藧���܂���B
��͂�A�������Ȃ��A�����܂��ȏ��Ŗ���������ق��A�Ȃ��̂ł��傤���c
��}�i�[�܂Ƃ߁�c�����͑�l�̗V�сB
��ŏq�ׂĂ������Ƃ��ꌾ�ł܂Ƃ߂�ƁA�v����ɁA�u�Â������ȁv�Ƃ������Ƃł��B ���͂ŏ������ɁA����̑ł����ɕ����t���A����̑����������邱�Ƃŏ����Ă��A����͎��͂ŏ������Ƃ͌����܂���B���̖͂����҂قǁA�A�h�o�C�X�Ƃ����`���Ƃ��āA���l�̑ł����ɂ��ꂱ��w�}���đ����������낤�Ƃ��܂��B���͂ł͏��ĂȂ�����ł��B���͂��Ȃ����瑫���������邱�Ƃł��������Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B �����Ȃ�ق��đł͂��ł��B�ア���瑼�l�̑ł����ɃS�`���S�`���w�}����̂ł��B�����͑�l�̗V�сB���_�I�ɐ��n������Ă��Ȃ��q�ǂ��͖��������Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��傤�B
���s���̂T�t�i��{�e�N�j�b�N�����ҁj
�����A������������x�łĂ�悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������狭���Ȃ肽���ł��ˁB�ȉ��ɂƂĂ��d�v�ŏ�Ɏg���e�N�j�b�N�����Љ�܂��B
��������b�e�N�j�b�N�R�匴����
�������@�F���R�̗��������Ď��������B�i�����Ȏ�������Ȃ��B�j
�������A�オ��Ȃ����͑S�̂�3/4������B�~��邱�Ƃ��������厖�B
�������B���A�Ԏl�P���A�F�ǂ݁A�s���t�肩�`�����^�n���z���C�c�n����������B
���u�����Q�v�ɂ��āc
���嗬�����ł�����݂́A��o�m��v���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
| �����͂S�l�ōs���Q�[���ł���A��Ƀ��C�o�����R�l���܂��B�P�R�U������n�C���A�����̂��߂����ɂ���̂ł͂Ȃ��A�S�l�ɔz������Ă��܂��킯�ŁA��l������͂��ł��S���̂P�������蓖�Ă��Ȃ����̂ł��B�����āA��ǂɂ����Ă�����̂���l�ŁA����܂��S���̂P�D�����ɂ��A�g�b�v����͂�P�l�ł��B
������ҁA���邢�̓g�b�v�ҁA�܂�v���[���[���ǂ����߂�ڕW�͂S���̂P�̐��E�A����������A�������S�{�̓�ւł��B���̂S���̂P��ǂ����߂�ƁA�����t�̂S���̂P�A�܂���e�҂�X�ɂȂ��Ă��܂��̂������̏�ł��B �������̂͂S���̂P�ɉ߂����A�����Ă��͂S���̂R�A�܂肠����Ȃ��ǂ̂ق��������̂ł�����A���͂�����Ȃ��ǁi�S�̂̂S���̂R�j�̂ق������d�v�ł��B�܂�A������Ȃ��ǁA�����ꂻ�����Ȃ��ǂŁA�����Ɏ��_��h��������ł��B ���l�ɁA�g�b�v���Ƃ�̂��S���̂P�Ȃ�A���X��H���̂��S���̂P�B�܂�A���X��H��Ȃ������S���̂R�Ȃ̂ł�����A����Ȃɂނ��������͂Ȃ��͂��Ȃ̂ł��B �i�������v������ł͓���ł��B�j �g�b�v���Ƃ邱�Ƃ���l���đł��Ă����l�ɂƂ��ẮA���̃��X���Ƃ�Ȃ��������Ƃ������z�͂Ȃ�������������܂���B�������A�g�[�^���I�Ɍ���A���X��H��Ȃ����������܂��A�g�b�v���Ƃ邱�Ƃɕ����Ȃ����炢�d�v�ȃe�N�j�b�N�ł��B ������Ȃ��ǂ͑S�̂̂S���̂R������A���̂R�l�������͎����Ƃ܂����������킯�Ȃ̂ł�����A����A�K���꒼���œːi���Ă��A�n�C�����̂悤�ɕ���ł��Ȃ��Ƃ��ɂ���������ŁA���ʂȂ��͖̂��ʂȂ̂ł��B ���Ƃ��e���p�C�܂ł����Ă��A�������Ƃ͌���Ȃ��̂������B�����邱�Ƃ₠���낤�Ƃ���C�������A�������ď����Ƃ̖W���ɂȂ邱�Ƃ������ł��B���̂�������ǂ��܂ŗ�Âɔ��f�ł��邩���A���͂̍��ƂȂ��Ă�����Ă��܂��B �u�ڂ돟�����邯�ǂڂ땉������l�v�Ƃ����̂͂��̃^�C�v���قƂ�ǂł��B |
���g�[�^�����ď����Ƃ�ڎw���B
��o�m��v���͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
| �u���́A�ꉞ�g�����v��"�ƌĂ�Ă��܂��B���ʁA�v���Ƃ�������A�}�̔��ł�����A�����E�Ƃ��Ă�����ƂȂ̂ł����A��������ƂƂ����Ă��A�����̏ꍇ�́A�Q�[���̏�ň��|�I�ȋ�����\���̂��ނ��������̂ł��B�v���Ȃ�A�A�}�Ƃ��ΑS�ǂ������ď�Ƀg�b�v��������܂��̃C���[�W���������̐l������悤�ł����A�S�l�Ő킢�A�����������Ȃ������Ƌ��R���̗v�f�����Ȃ葽�������ł́A���͂���Ȃ��Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł��B���������A���݂̃��[���ōl����A�����̔���1��͂��������S���t��1�z�[�����x���Ǝv���Ă�������������悤�B�ł�����A1�ǂ́A�S���t��1�łƂ������Ƃ���B1�ł����Ȃ�������A1�z�[�������ăA�}���v���ɏ����Ƃ͂�����ł�����͂��ł��B�g�b�v�E�A�}�ɂȂ�A18�z�[������Ă��v���ƍD�����ł��܂����A��������4���ԁA72�z�[���ł́A�A�}���v���ɏ������Ƃ����b�͂قƂ�Ǖ����܂���B�������A����Ȃӂ��ɍl���Ă���������A�[���������Ǝv���܂��B�o�����Ă̂����́A�Ƃɂ����A�K�邱�Ƃ��ړI�ƂȂ�܂����A���ۂɏ����Ƃ��Č����ꍇ�A�A�K���͒P�Ȃ��i�ł����āA�ړI�ł͂���܂���B����1���Ɍ���A�ړI�̓g�b�v�ł����A����1���̐킢�Ƃ����̂��A����������̂ł͂Ȃ��A����10���Ƃ������킢�ł���A10���̃g�[�^���ŏ����Ƃ�ړI�Ƃ��ׂ��Ȃ̂ł��B����1��P�ʁA���邢��1�ǒP�ʂŖ����������A�m��^�������Ƃ��čl�������Ƃ��A�����Ƃ����Q�[�����̂��̂𗝉����邱�ƂɂȂ����Ă���Ǝv���܂��B�v
|
�������J���`�̏d�v��
���ՂŁA�܂��n�C�����܂肻����Ă��Ȃ����A�ق��̃n�C�͍l�����A�}���Y�̂P�C�S�ƃs���Y�̂P�A�T���������Ƃ��܂��B��������s���t��_���ꍇ�ɂ͂��̂S���̂ǂ���̂Ă�̂��悢���Ƃ����ƁA�}���Y�̂P�ƂȂ�܂��B�s���Y�̂P�C�T�̓������J���`�̑O�i�K�ƌ��邱�Ƃ��ł��܂����A�}���Y�̂P�C�S�ł͂Q��R�������Ă����Ƃ��Ă��A�ǂ���ɂ��Ă��P�͂���Ȃ��Ȃ邩��ł��B
������L��
���Ղ͎�����L���Ƃ�ׂ��ł��B�S�����c�P�W�����g�E�̖ڈ������܂ł͈��ՂɃn�C��邱�Ƃ͔�����ׂ��ł��B
�R�ʂ܂��͍D�`
�R�ʑ҂��͍D�`�ɂ͈Ⴂ����܂��A�W�����g�E�����łɊm�ۂ���Ă���ꍇ�ɂ̓A���R�[�ׂ̗̃n�C�͐��Ă����܂��܂���B�����Ȃ��ƁA�c��̎�i�D�ɂ���ẮA�܂������Ӗ��̂Ȃ����Ƃ�����̂ł��B�l�����c��W�����g�E����ɓ��̂��݂ɕ`���Ă������Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B�i��������O����j
�A�������g�C�c���Q�g�̃������ʃ^�[�c�ƍl���悤
�����v�̃g�C�c�̏ꍇ�ɂ́A�V�����|���҂����ŏI�`�Ǝv��Ȃ��ŁA�ׂ̃n�C���c�����ă������ʂɂȂ�̂�҂��܂��傤�B
���a�_���̎�Â���
�s���t�͂S�����c�����ׂăW�����c�ō\������Ă��܂��B���������āA�s���t��ڎw������̍ۂɂ̓g�C�c���������܂��s��Ȃ���Ȃ�܂���B�W�����g�E�͈�ł悢�̂ł�����A�V�����|���`���c���K�v�͂Ȃ��̂ł��B
�h�����A���R�[�Ȃ�H
�h�����A���R�[�Ȃ�A���~�e���̂��������ڎw���āA�m���ɂ������悤�ɂ������B
�����[���ŕ��������_���̂���{
����͑��̎���ƃ_�u�点�邩�A���邢�̓h���𗍂߂Ă͂��߂č����_�ɂނ��т����̂ł��B
�O�F���H���Έ�n��
�s���R�ȎO�F�̓�n���Ȃ�A�s���t�A�h���P�ŏ\���ɃJ�o�[�ł���̂ł�����A������肷���Ȃ��悤�ɁB
�C�b�c�[�͂�����葹
�C�b�c�[�Ɋւ��Ă��A�O�F�Ɠ��l�A�s���R�Ȍ`�Ȃ�A������葹�̃P�[�X�������B�i�����Ƃ����Ă��邾���B�j
�V�����c���ł��ɂ����g�C�c��
���������郊�����ʌ`������Ȃ��悤�ȂƂ��ɂ́A�����Ă��A��Ƀg�C�c���Ԃ�����Ă�����̂Ȃ̂ł��B
�`�[�g�C�c�̓c���A�K�����L��
���Ƃɑł���Ȃ��댯�n�C�������āA�܂킵�ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�A�����A���̃n�C�̃^���L�҂��ł������悤�ɂ����čs�����߂ɁA�`�[�g�C�c�_���ɂȂ�܂��B�i��������O����j
�t�ɁA�`�[�g�C�c�ɂ͍U���I�Ȗʂ�����܂��B�Ƃ����̂��A�`�[�g�C�c�͓���v�Z�̂��߁i�����m�̒ʂ�j�o�A�K���ƃc���A�K���̃t�[�e�[�������ł���A���������āA�c���A�K���̓_�����m�ɏo�A�K���̓_�̔{�ɂȂ�킯�ł��B�܂�A�c���A�K��������߂ėL���Ȃ̂��`�[�g�C�c�ł��B
�t���e��
�肪������x�i�s�������ŁA�Ȃ��t���e�����c���Ă��邱�Ƃ͂��܂�D�܂������Ƃł͂���܂���
�h���ɂ�������Ă͂����Ȃ�
�h���������Ă���������������ʂł����Ə_��̂����v�ɂȂ�
���n�C�̃h����͏����̂Ƃ�
���n�C�̃h���Ȃ�A���Ƃ��|������Ă������������ł����v�̑̐��������Ă���Ƃ��ɁA�͂��߂Đ�o���̂ł��B�|������Ă���邭�炢�Ȃ�A�|�������Ȃ��Ńh��������Ă���邭�炢�̋C�ł����ق����A�ǂꂾ���������킩��܂���B
����̎�ւ�������
�e���p�C�̓S�[���ɂ��炸�ł��B�����Ȃ�ƁA���[�`�ɂ��Ă��A�����A�o�A�K���������Ȃ�����A�Ƃ������R�����ł̃��[�`�͂����Ȃ��Ȃ�܂��B�ꂵ���҂��ł�������A�������ʂւ̐U��ւ���҂��܂��傤�B�܂��A�f���炵����ɔ��W���鏊�܂Ō����Ă����̃��~�e���Ȃ̂ł��B
���[�`�̍l����
�u��������ȏ�A��ւ���҂K�v���Ȃ��v�Ɣ��f���A���A���̃��[�`���\�����ʓI�ł���ƔF�߂�ꂽ�Ƃ��A�͂��߂ă��[�`��������悢�B
���[�`�ɂ���
���ʓI�ȃ��[�`�������܂��傤�B
�����|�����[�`�̗ǂ�����
�����|���ɂ�����邠�܂�A�L�т����ӂ����ł��܂��̂ł͂��܂�悭�Ȃ���������܂���B�X�W�����|���́A�P�ɐl���ׂ�邽�߂����ɂ���̂ł͂Ȃ��A����Ȃǂ̑_�������Ȃ��邽�߂ɕK�v�łȂ��Ȃ����n�C�����R�ɗ��p������̂��ƍl���Ă��������B
�ꔭ����
������ꔭ���������߂̂Ȃ��ł����Ă��A���Ԃ�̎��������Ă܂ł���̂͂悭�Ȃ��ꍇ������܂��B
�������V�����J�C�z�E�̃^�C�~���O
�e���p�C�������_�ʼn��J������A���b�L�[�̉\�����łĂ��܂��B
���
������������Ȃ��Ƃ��ɁA�l�ɂ������点�Ȃ��悤�ɑł̂����ł��B
���킹����
���킹����������A�K���Ƃ���܂��B�܂��A�X�W�̂��킹�ł����Ȃ��Ȃ��L���ł��B
���NJԍۂɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����
�A�K���̉\���̂Ȃ��e���p�C�ɂ�������Ċ댯�n�C����������̂́A��ɐT�ނׂ��ł��B
�A���R�[�̃X�W�͊댯
�������ʂ̃X�W�n�C���N���Ɍł܂��Ă��܂��A���̃������ʃ^�[�c�������Ă���l�ɂ͂Ȃ��Ȃ����̃W�����c���������ɂ����Ȃ�܂�����A�e���p�C�����Ƃ��ɂ��̑҂����c��₷���ƌ�����ł��傤�B�Ƃ������Ƃ́A�X�W�n�C����������������Ȃ�A����͑��Ƃ̒N�����ق������Ă���v�A�܂�댯�n�C�ƍl������̂ł��B
���������肩�̔��f
�댯�n�C�����郊�����V�����e���Ȃ�A�����Ȃ��ق�������B
�o�����X
�悭�A���~�e���ł�����ƁA�u���[�`�����Ă�����ƍ��������̂Ɂv�Ȃǂƌ����l�����܂����A���[�`������Ώo����̂��o�Ȃ��Ȃ�A�ƍl���������悢�ꍇ����������܂��B���Ƃ��A�o�A�K���łT�Q�O�O�c���Ȃ�V�V�O�O���炢�̎�Ȃ�A�������}�`�ɂ����܂����A�����ōl����ƃ��[�`�͂��Ȃ��ق����悢�ꍇ�������ł��B
���ɂ��Ă����l�ŁA�Ⴆ�A���Ȃ��ŁA���m�~�����������i���Ȃ��l�������Ƃ��܂��B�����ł��A���̍Ō�̈ꖇ���o������A�u����������������Ȃ��v�ƍl����̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�܂���B����������ɍl������悤�ɂ��Ă����܂��傤�B
����������Ă���Ɩ{�l���C�Â��ʂ����ɓ��Ɍ�������Ă��āA��ÂȔ��f���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��悭����܂��B���̂悤�ȂƂ��ɁA���̓�����O�̂��Ƃɂ��C�Â����ɁA������A�K�낤�Ƃ��邩��A����ɕ��������ނ̂ł��I
���u�吔�̖@���v�ɂ��ā�
�Ⴆ�A�ꖇ�̃R�C��������Ƃ��܂��B���̃R�C���𓊂��āA�\�̏o��m���Ɨ��̏o��m���́A���ɂT�O���ł��B
�������A���Ƃ��A����R�C���𓊂����Ƃ��āA���̎�,�\���o���Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��A���̃R�C���𓊂��I�������_�ł́A���ʓI�ɂ́A�\�̏o���m���͂P�O�O���ƂȂ�A�T�O���ł͂���܂���B
�����āA�R�C���̓��ڂ𓊂����Ƃ��܂��B���̎��ɏo���̂��A���ɕ\�ł������Ȃ�A�\�A�\�ł�͂�A�\�̏o���m���͂P�O�O���ŁA�T�O���ł͂���܂���B
�������������̂��Ƃ����܂��ƁA���̂悤�ɁA��r�I�ɃR�C���𓊂��������Ȃ��̂Ȃ�A�{���T�O���ł���͂��̊m�����P�O�O����O���A�V�T���ȂǂƂ����A�������ꂽ�������o�邱�Ƃ̂ق����ނ��둽���A�t�ɁA�Ⴆ�A�P�O��R�C���𓊂����Ƃ��ĂT��A�T��ƁA�s�b�^���ɕ�����邱�Ƃ̕����A�ނ���H�Ȃ̂ł��B
�������A�P�Q�R�c�c�Ƃ�����ŁA�R�C���𓊂�����u����Ȃ�������v�ɋ߂Â��Ă����܂��B����ƁA�Ⴆ�R�C���𓊂������P�O�O����ł������Ȃ�A�P�O�O���ׂĕ\�A�ȂǂƂ������Ƃ́A�Ȃ��ɂقړ������Ƃ����܂��B�܂�A�m�����P�O�O����O���̂悤�ȋɒ[�Ȑ������o�邱�Ƃ́A�Ȃ��ƌ����Ă悢�̂ł��B
���̂悤�ɁA�R�C���𓊂��������Ȃ�������ɋ߂Â��Ă����Ȃ�A�\�i�܂��͗��j�̏o��m�����A����Ȃ��T�O���ɋ߂Â��܂��B�R�C���𓊂�����������Α����قǁA�m���͂T�O���ɋ߂Â��킯�ł��B
���̂��Ƃ��A���w�ł́u�吔�̖@���v�Ƃ����Ă��܂��B
�Ƃ���ŁA�����̎��͂��q�ϓI�ɑ�����@���A���̂��Ƃɂ���ĉ\�ɂȂ�킯�ł��B���_�\���ߋ��ɂ����̂ڂ��āA�̂ĂȂ��łƂ��Ă����킯�ł��B���̌l�l�̃v���X�ƃ}�C�i�X�𑫂��Ă����܂��傤�B
���̂Ƃ��ɏo���������A���̂ЂƂ̎��͂������Ă��܂��B�{�l��������u�����͉^���B�v�Ƃ��������ŁA�m�����v�w�̑�藝�u�吔�̖@���v�ɂ���āA�ؖ�����Ă��܂��̂ł��B
���Ȃ��̎���́A�g�[�^�����ăv���X�̐l�͒N�ł��傤���H�t�ɁA�g�[�^���Ń}�C�i�X�̐l�́c�H
���e���p�C���j��
�����A������x�����ɂ��Ȃ�Ă��܂����B�����Ă�����x�\���I�ɑł��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�����A���͑��ƂɃt���R�~�����Ȃ��ׂ̍ŏd�v�e�N�j�b�N�A�u�e���p�C���j��v�ł��B����̃e���p�C�ƁA���̑҂��v�����j���悤�ɂȂ�A����ɐU�荞��ł��܂��悤�Ȃ��Ƃ��O�b�ƌ���܂��B�����ŁA��肪3/4�ł��������Ƃ��v���o���Ă��������B���̃e���p�C���j��̋Z�p�͂��Ȃ�d�v�ł��邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B
�ȉ��͋Z�p�I�ȃe���p�C���j��̌����ł����A��F�����ēǂݎ��Z�p�͌�q���܂��B
��e���p�C�ǂ�
��{�O�匴����
�����@���X�W��m��B
�����A���a�nor�`�����^�n��������B
�����B�F�ǂ݂�����B
��`�[�g�C�c�͂ǂ̂悤�Ɍ������邩��
�˗Ⴆ�A�̂Ĕv�����āA���n�C�����o���Ă��Ȃ���A���̂��Ƃɐ^�̃n�C���ڗ��Ȃ�A�u�g�C�c�`�̎�v���l������̂ŁA�`�[�g�C�c��g�C�g�C���x���������B�܂��A�̂ăn�C�Ƀg�C�c���ڗ��̂��g�C�c�`�̎�̓����B
��Ԏl�P���̓_�u���̗��X�W��
�˗Ⴆ�A�Q�ƂV���̂ĂĂ�������A�R�C�U���_�u���ŗ��ɂȂ��Ă���B�������A�댯�x��B
������E���������猩�j�遚
��t��w���_�����̑��P�搶�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
| ����̈ꋓ�ꓮ�ɋC��z��A�܂��A����̃n�b�^����A�V���~�Z����K���ɂƂ炦�āA�����Ă̎���̑傫���𐄂��ʂ�A�҂����Ŕj���Ă������B ���̍ہA��Ȃ��Ƃ́A����̂ӂ���̃e���|�╁�i�̓�������������ǂݎ���Ă������Ƃł���B ����A���ԂɃp�C�������Ď̂Ă�B���̈ꌩ�P���ȓ���̌J��Ԃ��̊ԂɁA�l�́A���ɗl�X�Ȏ肪�����^���Ă����B����l�́A�����̎�̒��̃p�C���������������݂����A�J�`�J�`�ƃp�C�ʼn��𗧂Ă�B����l�́A�Â��Ƀ^�o�R��h�炵�A���X�������̃r�[�������ށB�܂�����l�́A�ނ��艟���ق��āA�فX�ƃp�C�����A����l�́A�펞����ׂ�܂���A�n�b�^���A�܂��́A����������B �ǂ�Ȑl�ł��A�������ɖ����ɂȂ��Ă���Ƃ��ɂ́A���낢��Ȏd���ŁA�Ɠ��̕Ȃ��I����B���邢�́A���Ȃ��Ƃ��A���̐l�̍s���̌l�I�e���|��A���Y����������Ă���B���́A�l�I�e���|�Ȃ�A�ȂȂ���A������Ƃ������Ă������Ƃ��A�܂��K�v���B �ώ@�̃|�C���g�́A�v���C����R�l�i�S�l�j�̐l�́A�\��ω��͂ނ��̂��ƁA�b�̓��e�A�e���|�Ȃǂ̂ق��A���C�Ȃ��A�@�������������A����Ȃł��肷�铮��ɂ�����܂ŁA�Ȃ邽���ׂ����`�F�b�N���Ă����̂��悢�B���Ƃ��A����l���^�o�R��{����������ɂ��Ă��A������z������܂ł̎��ԂƂ��A���̉��̓f�����A�D�̏����̎d���A�̂ăn�C������p�x�A�ڂ̓��E�̊J����A���̒���A�n�R�䂷��A�ȂǁA�ώ@���ׂ��v�_�͂�����ł�����B �������Ċώ@���Ă����ƁA�ȑO�́A���ʂ̂Ƃ��̌l�I�s���e���|��A�����X���Ȃǂ��A���Ȃ�͂����肵���`�ŗގ������邱�Ƃ��ł���B�����āA���ɁA���̐��펞�̃e���|��s�����A��펖�Ԃɂ����āA�����ɕω����Ă��������A�K���̎��̖��̑傫���ƊW�����āA�ώ@���Ă����悢�킯�ł���B ���Ƃ��A�}���K�����e���p�C�����Ƃ��A�����̐l�́A�p�C���c����ɂ�����Ɏv�킸�͂�������A��悪�������ɂӂ邦��ттĂ���B�炩��͌��̋C�������āA���������ƂȂ�A���A�z�̘e�ɁA���ǂ������o���Ă���悤�Ȑl���ƁA�����ɏ]���Ă��̕ӂ肪�A�Ђ��Ђ����z�����N�����A�Ƃ��ɂ́A��������Ɩ��ł��Ă���B�������A�����l���G�Ɍ���܂��Ƃ��āA���肰�Ȃ��U�������Ƃ������قǁA�̂̕\�o�́A�܂��܂��������Ȃ�̂����ʂł���B���}�����e���p�C�����Ƃ��A�����̐l�́A�Ȃɂ���������̂Ȃ���k���������Ƃ��邪�A�����������悤�ɂȂ��āA�����̌y�����q���o�Ă��Ȃ��B�l�̑ł����ɁA�������������C�`�����������Ă���l���A�}�ɂȂɂ�����Ȃ��Ȃ�A�����̎���ɏW�����n�߂�B�܂��A��Ƃ�������āA�^�o�R�ɉ����悤�Ƃ���A�͂��ł݂�ڂ������������炢�ɁA�^�o�R�̐悪�A�Ԃ�Ԃ�k���Ă���B����ɋ������Ђǂ��Ȃ�ƁA���_�������ɂ���āA�p�C���c����肪�����Ƃ�Ɗ��݁A���̂��߁A�p�C���ʂꂽ�悤�ɂȂ邱�Ƃ�������B�܂��A�l�ɂ��ƁA�ނ�݂ɐ��������傳��Ă��āA�����育����ƁA���������Ȃ��悤�ɁA�����ݍ���ł���B�܂�����l�́A�e���p�C�����̂����j���Ȃ��悤�ɂƁA�����ɂ��e���p�C���Ă��Ȃ��悤�Ȃ��Ԃ�ŁA�킴�Ƃ炵���̂ăn�C�߁A����Ă��銴�����������Ƃ���B ����قnj������\�o�Ȃ�A�N�ɂ������邪�A���̂ق��A��r�I�悭�ώ@�����̂́A���t�̃e���|�Ɠ��e�ł���B���܂ŁA����܂����Ă����l���A�}�ɖق肱�����Ă��܂�����A�ނ��艮���A��������ׂ�o�����Ƃ��́A���ɒ��ӂ��̗p�ł���B���l�ɁA�����̓��e�ɂ��Ă��A�悭�C�����Ă���ƁA�����ĊO�A�{���̂��Ƃ���k�܂���Ɍ����l�A�t�ɁA�{���̂悤�Ȍ������ʼnR�������l�A�ȂǂƂ����悤�ɁA�ތ^�͈ȊO�ɊȒP�Ȃ��̂ł��邩��A���ꂪ�i�D�̎肪����ƂȂ�̂ł���B |
���̑��A�ȒP�Ƀe���p�C�����j����@�������܂��傤�B�����Ƃ���{�̓ǂ݂ŊȒP�Ŋm���ȕ��@�ł��B
���ɑf�l�ɑ����̂ł����A
�����̎�v���K�`���K�`���Ƃ������Ă��đ��Ƃ̎̂Ĕv�����܂�ӎ����Č��Ă��Ȃ�����́A�܂��e���p�C�����Ă��Ȃ����Ƃ������ł��B
�t�ɁA��v���K�`���K�`���Ƃ����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�̂Ĕv������Ȃ����ׂČ��Ă���l�̓e���p�C���Ă����\�������ɍ����Ƃ����܂��B
�f�l�ł͂Ȃ��Ȃ�ƁA���̂悤�ɓǂ܂�邱�Ƃ��l���āA��Ȃ��悤�ɍs�����܂����c�B
�����Ƃ���
�����͖{���ɉ����[���Q�[���ł��B�����̗��_�I�Ȃ��̂�������x�}�X�^�[�����Ƃ��Ă��A����ɐl�ԓ��m�̐S���I�ȗv�f������ł��邽�߂ɁA�������ɂ߂悤�Ǝv�����炫�肪����܂���B�l�b�g��ł͖����͏�ɑ�l�C�̃Q�[���ł����A��w���Ȃǂ��O������Ă܂Ŗ��������Ă��܂��B���ꂾ�������[���Ėʔ����Q�[���ł��̂ŁA���ЁA�l���̒��̂�������̌�y�̈�Ƃ��āA�y����ł������ł͂���܂��B�O�O
�����܂œǂ�ł��������Ăǂ������肪�Ƃ��������܂����Bm(_ _)m(�Ǘ��l)
1998�N3��24��
�������N�t���[�ł���T�C�g�쐬�ɂ��𗧂ĉ������B��